もっと快適にもっと心地よく眠るための情報。 快眠のコツ を知って、眠りを極める。 快眠のために重要となる、睡眠の質に関して。 レム睡眠とノンレム睡眠 など。
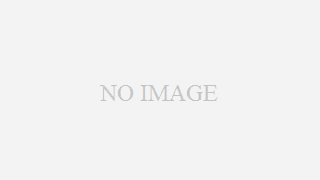 睡眠の質
睡眠の質 質のいい眠りのためには夕方~夜の軽い運動が必須
適度なスポーツが睡眠の貿を上げてくれます ゴルフや水泳、ジョギング、ヨガ。昼間にからだを動かして気持ちいい汗をかいた夜、ぐっすり眠れた経験はありませんか?運動をした日はよく眠れる。なんとなく常識で「そんなの当た旦削だろう」といわれてしまいそ...
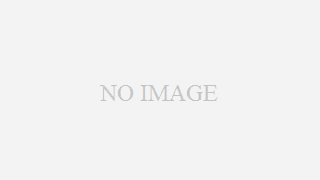 睡眠の質
睡眠の質 ぬるめのお風呂でぐっすり眠り、 朝の熱いシャワーでスッキリ目覚める
寝苦しい夜は、風を通して寝具にもひとエ夫を 40度を超える猛暑や予測のつかないゲリラ豪雨など、「経験したことのない」現象がニュースになる時代です。冬の寒い時期に冷たい布団の中で眠りにつくのもなかなか大変ですが、夏の蒸し暑さも、寝付けない、熟...
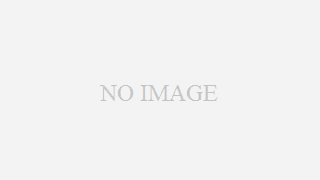 睡眠の質
睡眠の質 働き盛りの30~50代が 眠りに関するトラブル が多く悩みを抱えている
若い頃のように快眠できないのは? 「学生時代や新入社員のころはよく眠れたのに、今は途中で夜中に目が覚めたりして…」というのはよく言われることです。 「どうすれば ぐっすり眠ったな と思えるような熟睡ができるようになるのでしょうか? 実際、こ...