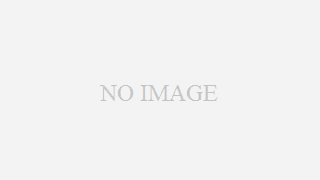 賢い眠り方
賢い眠り方 仮眠で脳の疲れをとる
ちょっとした時間にとる仮眠は、睡眠不足の解消のほかにも意外な効果をもたらします。昼寝で脳が活性化するそれは、『シエスタ』といわれる昼寝をする習慣で、スペインやイタリアなどでは生活の一部となっています。この地方に暮らす人々の間では、仕事をして...
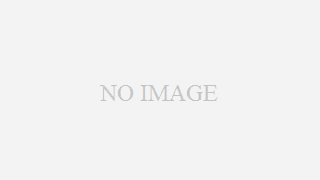 賢い眠り方
賢い眠り方 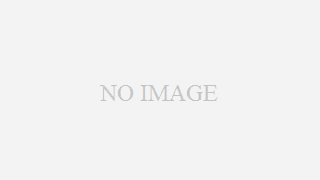 賢い眠り方
賢い眠り方 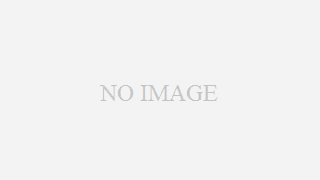 賢い眠り方
賢い眠り方