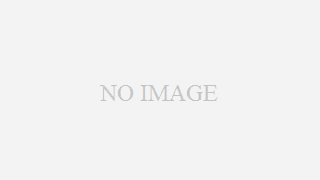 快眠のコツ
快眠のコツ 女性の 快眠 ホルモンコントロール が有効
女性の 快眠 ホルモンコントロール が有効だというのをご存じでしょうか。働く女性が急増し、当たり前になった最近では、女性の不眠には女性ホルモンとの関係性をしっかり考えられた快眠方法が有効であることがわかってきました。 女性の 快眠 ホルモン...
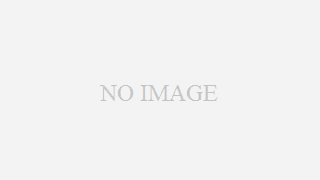 快眠のコツ
快眠のコツ 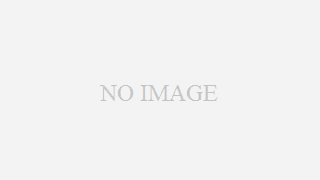 賢い眠り方
賢い眠り方 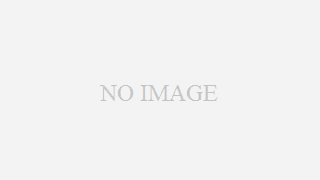 賢い眠り方
賢い眠り方